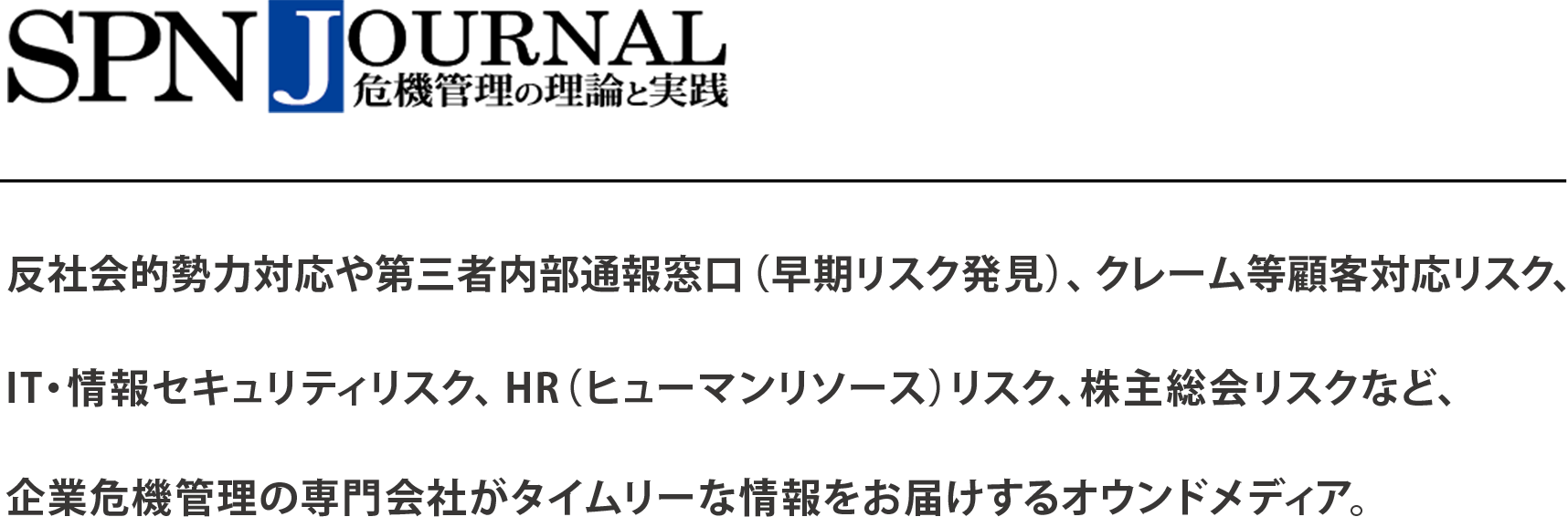記事一覧
-

SPNの眼
地震や火災が起きたら、まず何をしたらいいのだろう~自衛消防組織について再確認しよう~(後編)
2025.03.31 -

危機管理トピックス
損害保険会社4社に対する行政処分について/業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル/地方財政白書/テレワーク人口実態調査結果
2025.03.31 -

HRリスクマネジメント トピックス
「私の評価に納得できない!」SPNの森 動物たちが語るHRリスクマネジメント相談室
2025.03.24 -

危機管理トピックス
厚生労働省関係の主な制度変更/ギャンブル等依存症対策推進基本計画/インターネット上の違法・有害情報に関する流通実態アンケート調査
2025.03.24 -

情報セキュリティ トピックス
情報セキュリティを高めるために、今できること(IPA 情報セキュリティ10大脅威 2025)
2025.03.18 -

危機管理トピックス
開発協力白書/サイバー空間をめぐる脅威の情勢/少年非行及び子供の性被害の状況
2025.03.17 -

暴排トピックス
体感治安の悪化を食い止めよ~トクリュウ・SNS・匿名化・犯罪インフラ対策・連携が肝となる
2025.03.10 -

危機管理トピックス
AIディスカッションペーパー/犯罪収益移転防止に関する年次報告書/デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス
2025.03.10 -

SPNの眼
地震や火災が起きたら、まず何をしたらいいのだろう~自衛消防組織について再確認しよう~(前編)
2025.03.04 -

危機管理トピックス
犯罪収益移転防止法施行規則改正/中堅企業成長ビジョン/企業行動に関するアンケート調査結果/自殺対策強化月間
2025.03.03
30秒で読める危機管理コラム
危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。
03月31日号
組織犯罪の進化には国際連携の深化で対抗せよ
SNSなどを通じ財産をだまし取るオンライン詐欺被害が世界の治安を脅かしている。2024年の日本国内の被害額は2000億円に迫り、米英も深刻だ。背景には、犯行の全ての過程をインターネット空間で完結できるようになったことが挙げられる。デジタル化で利便性が高まったサービスを犯罪組織が悪用、ますます第三者の目が届きにくく、被害の未然防止は難しくなっている。抑止には犯罪組織の摘発が最も効果的だが、各国の捜査機関単独による活動には限界がある。オンライン詐欺は被害者がいる国に犯行拠点を置く必要がない越境犯罪であり、首謀者は捜査を逃れるため国境を越えた移転を続けているからだ。こうした中、日本とASEANは2025年4月にも実務者レベルの会議を新設するという。1国(点)での限界を広域(面)で乗り越えようとする国際連携の深化に期待したい。(芳賀)
ミャンマー地震の研究
3月28日にミャンマー中部で発生した大地震。軍部の発表ではおよそ1700人が死亡したとしているが、一部報道では犠牲者1万人を超える可能性もあるとしており予断を許さない。現地ではまだ救出作業が続いているため、まずは1人でも多くの救助を願う。ところで、このミャンマー中央部を南北に縦断するサガン断層について、「歴史地震」(2011年)のなかで古川信雄氏が詳細に報告している。この断層上や近辺では1912年を始め、数多くのマグニチュード7クラスの地震が発生しており、特に1930年前後には同クラスの3地震がミャンマー南部で連続発生し、多大の被害が生じた。その上で同氏は「サガン断層上の中部領域では1904年以降M7以上の地震が発生しておらず、ミャンマー国内のサガン断層上唯一の地震空白域である」と指摘。今回の地震に警鐘を鳴らす形となった。(大越)
▼[講演要旨]プレート境界である、ミャンマーのサガン断層近傍のM7クラス歴史地震(1918年以降)の震源再決定によるサガン断層の地震履歴
やってみないとわからないこと、ずっとやっているとわからなくなること
夕飯の後の食器洗いが苦痛だ。「料理は妻、片づけは夫」で家事分担している家の話をよく聞くが、我が家はキッチン回りが筆者の担当。料理も片づけもしていて思うのは、夕飯は「作るより片づける方がつらい」ということ。仕事から帰って、そのままの勢いで料理をはじめるのは、実はさほど苦にならない。一度座ってくつろいでしまうと、もう一度立ち上がって家事を始めるのがつらいのだ。「料理する」に比べたら、「ただ片づけるだけ」に見えるかもしれない。だが、やってみないとわからない苦労がある。一方で、ずっと当たり前のように続けていると、苦労に気付けなくなることもある。これが普通と思い込めば、あえて苦労を解消しようとも思わないだろう。きっと仕事も同じ。たまにはフレッシュな視点での振り返りや、互いの苦労への感謝をすべきと思う。(吉原)
代替策ではごまかせず、責任の所在を再考すべき~大阪高裁の同性婚違憲判決を例に~
日本で同性婚が法的に認められていないことについて、3月25日、大阪高等裁判所は「性的指向による不合理な差別だ」として違憲と判断した。この判決で注目すべきは、一審で合憲の根拠になっていた自治体の「パートナーシップ制度」に言及し、根拠なく区別する制度はむしろ新たな差別を生み出すおそれがあるとし、現行法は「個人の尊厳」に立脚した婚姻制度を求める憲法第24条第2項と「法の下の平等」を求めた第14条第1項に反するとした点だ。「代替策があればいい」との考えを否定し、自治体レベルでできることの限界を示しているようだ。そもそも、自治体はその地域に根差した施策を講ずるもので、同性婚を認めるかどうかは、地域性と無関係だ。同性パートナーの「暮らしやすさ」の追求は自治体が担うにしても、同性婚制度については国の責任だろう。(安藤(未))